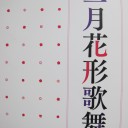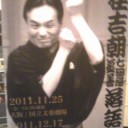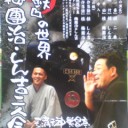京都・南座で『秀山祭(しゅうざんさい)三月大歌舞伎』を観て来ました。
“秀山”とは初代・中村吉右衛門の俳名で、
初代の生誕120年を記念して2006年9月に歌舞伎座で行われたのが始まり。
東京以外での公演はこれが初めてだそうです。
南座は松竹座と違って“幕見”が無いので、
年末の『顔見世』以外で歌舞伎を観に行くことはおそらく10年以上ぶりのこと。
当代の中村吉右衛門演ずる『俊寛』が観たかったので、
意を決して?チケットを購入(3階席の最上段)しました。
その『俊寛』の話。
平家打倒の企てが平清盛に知られたことで、
鬼界ヶ島に流刑となった俊寛僧都、丹波少将成経、平判官康頼の3人。
以来3年、細々と島で暮らして来て、
成経には島の海女である千鳥という恋人が出来ています。
或る日、都から赦免の使者を乗せた船が鬼界ヶ島へやって来て、
使者の瀬尾太郎兼康が赦免状を読み上げますが、
都へ帰ることを許されたのは成経と康頼の2人。
清盛の俊寛に対する憎悪の念があまりに深かったため、俊寛だけ残されることに。
同じ罪によって同じ場所へ流されたのになぜ自分だけが、と嘆く俊寛でしたが、
あとで現れたもう一人の使者、丹左衛門基康が清盛の長男・重盛の意として、
俊寛も船に乗って備前まで戻ることになりました。
これに喜んだ3人は、千鳥を伴って船に乗り込もうとしますが、
瀬尾は千鳥の乗船を許しません。
千鳥を乗せられないなら4人揃って島に残る、と言い出したのを見て、
丹左衛門が俊寛らの願いを聞いてやろうとするものの、
瀬尾は「罪人を船に乗せて帰すのが我々の仕事、あとは知らん」とばかりに拒否。
さらに俊寛に向かって、俊寛の妻が清盛に殺されたことを告げます。
妻を殺されて都へ戻る希望を失った俊寛は、
自分は島に残るから千鳥を船に乗せてやってほしいと瀬尾に懇願しますが、
瀬尾は頑として受け付けません。
思い余った俊寛、瀬尾の刀を引き抜いて瀬尾に斬りかかります。
斬られた瀬尾は船上の丹左衛門に助けを求めますが、
丹左衛門は「罪人を船に乗せて帰すのが我々の仕事、あとは知らん」というわけで、
その場面をじっと見守るばかり。
瀬尾を討ち取った俊寛。
その思いを丹左衛門は汲み取って、俊寛の代わりに千鳥の乗船を許します。
船は浜辺から島を離れ、俊寛は船に向かって手を振り続けますが、
島に残る決心をしたとは言え思い切れずに船の後を追ううちに波に戻され、
岩の上へと這い上がって去りゆく船を見送るのでした・・・。
『俊寛』は吉右衛門の当たり役、と各方面から評されています。
歌舞伎というのは言わば“様式美”の世界ではあるのですが、
『俊寛』や『曽根崎心中』など近松門左衛門の作品はどれも人間描写が豊かで、
役者もそれなりにリアルな表現が要求されます。
それでいて現代劇ではなく歌舞伎ならではの演出を表に出すわけですから。
俊寛が遠ざかる船を必死で追おうとしているところで、
浄瑠璃が「思い切っても凡夫心(ぼんぷしん=平凡な人の心)」と語り、
花道から波の模様がスルスルと舞台に向かい俊寛の行く手を阻む。
やっとの思いで岩に上がって、遠ざかる船を万感の思いで眺める。
このシーンだけでも涙がじんわり滲み出て来るぐらいで、
鬼気迫る演技、とはまさにこのことかと思います。
また、今回の秀山祭では、
中村歌昇改め三代目中村又五郎、中村種太郎改め四代目中村歌昇、と
親子同時の襲名披露がありました。
夜の部にその“口上”もあったのですが、
いつもの芝居がかった口調だけではなく役者さんの“素”も出たりするので、
これもなかなか楽しかったです。
“秀山”とは初代・中村吉右衛門の俳名で、
初代の生誕120年を記念して2006年9月に歌舞伎座で行われたのが始まり。
東京以外での公演はこれが初めてだそうです。
南座は松竹座と違って“幕見”が無いので、
年末の『顔見世』以外で歌舞伎を観に行くことはおそらく10年以上ぶりのこと。
当代の中村吉右衛門演ずる『俊寛』が観たかったので、
意を決して?チケットを購入(3階席の最上段)しました。
その『俊寛』の話。
平家打倒の企てが平清盛に知られたことで、
鬼界ヶ島に流刑となった俊寛僧都、丹波少将成経、平判官康頼の3人。
以来3年、細々と島で暮らして来て、
成経には島の海女である千鳥という恋人が出来ています。
或る日、都から赦免の使者を乗せた船が鬼界ヶ島へやって来て、
使者の瀬尾太郎兼康が赦免状を読み上げますが、
都へ帰ることを許されたのは成経と康頼の2人。
清盛の俊寛に対する憎悪の念があまりに深かったため、俊寛だけ残されることに。
同じ罪によって同じ場所へ流されたのになぜ自分だけが、と嘆く俊寛でしたが、
あとで現れたもう一人の使者、丹左衛門基康が清盛の長男・重盛の意として、
俊寛も船に乗って備前まで戻ることになりました。
これに喜んだ3人は、千鳥を伴って船に乗り込もうとしますが、
瀬尾は千鳥の乗船を許しません。
千鳥を乗せられないなら4人揃って島に残る、と言い出したのを見て、
丹左衛門が俊寛らの願いを聞いてやろうとするものの、
瀬尾は「罪人を船に乗せて帰すのが我々の仕事、あとは知らん」とばかりに拒否。
さらに俊寛に向かって、俊寛の妻が清盛に殺されたことを告げます。
妻を殺されて都へ戻る希望を失った俊寛は、
自分は島に残るから千鳥を船に乗せてやってほしいと瀬尾に懇願しますが、
瀬尾は頑として受け付けません。
思い余った俊寛、瀬尾の刀を引き抜いて瀬尾に斬りかかります。
斬られた瀬尾は船上の丹左衛門に助けを求めますが、
丹左衛門は「罪人を船に乗せて帰すのが我々の仕事、あとは知らん」というわけで、
その場面をじっと見守るばかり。
瀬尾を討ち取った俊寛。
その思いを丹左衛門は汲み取って、俊寛の代わりに千鳥の乗船を許します。
船は浜辺から島を離れ、俊寛は船に向かって手を振り続けますが、
島に残る決心をしたとは言え思い切れずに船の後を追ううちに波に戻され、
岩の上へと這い上がって去りゆく船を見送るのでした・・・。
『俊寛』は吉右衛門の当たり役、と各方面から評されています。
歌舞伎というのは言わば“様式美”の世界ではあるのですが、
『俊寛』や『曽根崎心中』など近松門左衛門の作品はどれも人間描写が豊かで、
役者もそれなりにリアルな表現が要求されます。
それでいて現代劇ではなく歌舞伎ならではの演出を表に出すわけですから。
俊寛が遠ざかる船を必死で追おうとしているところで、
浄瑠璃が「思い切っても凡夫心(ぼんぷしん=平凡な人の心)」と語り、
花道から波の模様がスルスルと舞台に向かい俊寛の行く手を阻む。
やっとの思いで岩に上がって、遠ざかる船を万感の思いで眺める。
このシーンだけでも涙がじんわり滲み出て来るぐらいで、
鬼気迫る演技、とはまさにこのことかと思います。
また、今回の秀山祭では、
中村歌昇改め三代目中村又五郎、中村種太郎改め四代目中村歌昇、と
親子同時の襲名披露がありました。
夜の部にその“口上”もあったのですが、
いつもの芝居がかった口調だけではなく役者さんの“素”も出たりするので、
これもなかなか楽しかったです。
歌舞伎らしからぬ歌舞伎@松竹座。
2012年2月12日 趣味
道頓堀・大阪松竹座で『二月花形歌舞伎』昼の部を観て来ました。
片岡愛之助、市川染五郎、中村獅童。
今をときめく花形役者3人(しかも同学年)の揃い踏みです。
昼の部の演目は『慶安の狼』と『大當り伏見の富くじ』の2つ。
歌舞伎という固定観念を打ち砕くには充分過ぎる内容でした。
『慶安の狼』は“由井正雪の乱”を題材にして、
槍の名手・丸橋忠弥の苦悩を描いた作品。
幕間などに流れる音楽はオーケストラ調のもので、
“歌舞伎”よりも“時代劇”の様相です。
(初演は“新国劇”だったそうで)
ラストの回り舞台を使っての大立ち回りも、
歌舞伎の様式美的なものではなく実に激しくリアルでした。
忠弥を演じたのは中村獅童。
枠に捕らわれない奔放さの中に垣間見える繊細な心情がよく出ていたと思います。
容貌は古典的なんですが、こういう芝居のほうが獅童には似合います。
忠弥の古くからの友人・小弥太の片岡愛之助も、口跡がとても爽やかでした。
『大當り伏見の富くじ』は、想像をはるかに超えるぶっ飛びぶり(笑)
照明や演出が非常に現代的で、
遊女3人がEXILEのマネをしてグルグル回ってみたり、
「承知しました」というセリフに「ミタさんか!」とツッコミが入ったり。
随所随所に“当世”の小ネタを散りばめているだけでなく、
歌舞伎でお馴染みのセリフや仕草を取り入れるなど、
歌舞伎を知っている人にも知らない人にも楽しめる演出がありました。
ラストは出演者が揃って、それぞれの衣装や着ぐるみのままでダンスを披露。
(ぽいぽいぽいぽぽぽいぽぴー♪みたいな振り付けもあり)
カーテンコールまでありました。
やや冗長なところはあったにせよ、
新しい時代の歌舞伎を感じさせる楽しい舞台でした。
主役の紙屑屋は市川染五郎。
思っていたほど上方言葉に不自然さは無かったです。
“ちょっと足りないけど品のある若旦那”を嫌味なく演じていました。
番付(パンフレット)の表紙には、
よく見ると“初心者マーク”らしきものがあしらわれています。
2月なので“鬼”も居たりして(笑)
こういった遊び心も楽しいものです。
片岡愛之助、市川染五郎、中村獅童。
今をときめく花形役者3人(しかも同学年)の揃い踏みです。
昼の部の演目は『慶安の狼』と『大當り伏見の富くじ』の2つ。
歌舞伎という固定観念を打ち砕くには充分過ぎる内容でした。
『慶安の狼』は“由井正雪の乱”を題材にして、
槍の名手・丸橋忠弥の苦悩を描いた作品。
幕間などに流れる音楽はオーケストラ調のもので、
“歌舞伎”よりも“時代劇”の様相です。
(初演は“新国劇”だったそうで)
ラストの回り舞台を使っての大立ち回りも、
歌舞伎の様式美的なものではなく実に激しくリアルでした。
忠弥を演じたのは中村獅童。
枠に捕らわれない奔放さの中に垣間見える繊細な心情がよく出ていたと思います。
容貌は古典的なんですが、こういう芝居のほうが獅童には似合います。
忠弥の古くからの友人・小弥太の片岡愛之助も、口跡がとても爽やかでした。
『大當り伏見の富くじ』は、想像をはるかに超えるぶっ飛びぶり(笑)
照明や演出が非常に現代的で、
遊女3人がEXILEのマネをしてグルグル回ってみたり、
「承知しました」というセリフに「ミタさんか!」とツッコミが入ったり。
随所随所に“当世”の小ネタを散りばめているだけでなく、
歌舞伎でお馴染みのセリフや仕草を取り入れるなど、
歌舞伎を知っている人にも知らない人にも楽しめる演出がありました。
ラストは出演者が揃って、それぞれの衣装や着ぐるみのままでダンスを披露。
(ぽいぽいぽいぽぽぽいぽぴー♪みたいな振り付けもあり)
カーテンコールまでありました。
やや冗長なところはあったにせよ、
新しい時代の歌舞伎を感じさせる楽しい舞台でした。
主役の紙屑屋は市川染五郎。
思っていたほど上方言葉に不自然さは無かったです。
“ちょっと足りないけど品のある若旦那”を嫌味なく演じていました。
番付(パンフレット)の表紙には、
よく見ると“初心者マーク”らしきものがあしらわれています。
2月なので“鬼”も居たりして(笑)
こういった遊び心も楽しいものです。
“桜”と“引き抜き”。
2012年1月15日 趣味日本橋・国立文楽劇場の『文楽初春公演』と、
道頓堀・大阪松竹座の『壽 初春大歌舞伎』で、
“幕見”のハシゴをして来ました(笑)
文楽劇場では『義経千本桜』の二幕目・河連法眼館(かわつらほうげんやかた)の段を
11時49分から13時まで、1,500円。
松竹座では『積雪恋関扉(つもるゆきこいのせきのと)』を14時10分から15時40分まで、
2,100円でした。
ここでは文楽の話を中心に。
今回の『義経千本桜』は“道行”と“河連法眼館”の2部構成。
“河連法眼館”は“狐忠信(きつねただのぶ)”とも呼ばれたりしていて、
歌舞伎でも人気のある演目です。
兄・頼朝から追われの身になった義経は、
幼いころに兵法を学んだ河連法眼の吉野の屋敷に匿われていました。
そこに訪ねて来たのが、家来の佐藤忠信。
母の看病で故郷に帰っていて、ようやく義経の前に顔を出すことができたと言うのですが…
義経は吉野への道すがらで忠信に静御前を預けたと思っています。
それを尋ねると忠信は預かった覚えはないとのこと。
怒った義経は目の前の忠信を裏切り者と決めつけて罰しようとしていたところ、
静御前がそこへ一人で現れました。
静御前の話によると、肌身離さず持っていた鼓を打つと忠信が必ず姿を見せ、
その音に聞き入っていたようです。
義経はそれを確かめるために静御前に鼓を打たせ、自らは奥でその様子をうかがうことに。
そこに白い狐がスーッと通り過ぎたかと思えばいつの間にか忠信が現れたので、
静御前は刀を振り上げてその正体を明かすように迫ります。
静御前が持っているその鼓は・・・桓武天皇の時代、
雨乞いのために千年も生きたオスの狐とメスの狐を狩り出してその皮で作られたもので、
自分はその鼓の子なのだと白状して狐の正体を現します。
長く天皇家にあったその鼓は平家討伐の恩賞として義経に下されたあと、
静御前の手に渡ったのですが、せめて鼓になった両親に孝行をしたいとの思いで
忠信に化けて静御前のお供をしていたのです。
これを聞いた義経が、静御前を守った褒美として狐に鼓を与えると、
喜んだ狐は義経一行が危機にあっても神通力で守ると言い残し、
鼓とともに天高くその場を去って行く・・・という筋書きです。
歌舞伎では忠信から狐への早替わりと、
狐が去るときの“宙乗り”という演出(役者が上から吊られた状態で花道を下がる)で、
市川猿之助や中村勘九郎(現・勘三郎)などが得意としていました。
(私は猿之助のそれでかなりの衝撃を受けたものです)
では、文楽ではどうだったかと言えば。
狐をやっていた人形遣いの桐竹勘十郎が舞台狭しと縦横無尽の大活躍。
人形の早替わりだけでなく、人形遣いの衣装も一瞬で替わります。
そして勘十郎自身も舞台で“宙乗り”を演じ、桜の花びらを散らしながら幕、という
文楽のイメージをはるかに超えるかのようなラストシーンは圧巻そのものでした。
衣装の早替わりは、付けられている糸を引っ張って一瞬に替わることから
“引き抜き”と呼ばれています。
歌舞伎ではよくある演出ですが、文楽の人形遣いの“引き抜き”は初めて見ました。
そのあと松竹座で観た『積恋雪関扉』は“引き抜き”満載の舞踊劇。
樹齢300年と言われる“小町桜”をめぐってのやりとりで、
逢坂山の関守が実は朝廷転覆を企む大伴黒主(市川團十郎)であり、
関守に会いに来たという遊女が実は小町桜の精(坂田藤十郎)という設定。
それぞれの豹変ぶりがとても絵になっていました。
ただ、この演目はちょっと難しいのか、居眠りするお客さんがチラホラと・・・。
というわけで、
偶然にも“桜”と“引き抜き”という共通点のあった、
今回のハシゴ観劇でした。
道頓堀・大阪松竹座の『壽 初春大歌舞伎』で、
“幕見”のハシゴをして来ました(笑)
文楽劇場では『義経千本桜』の二幕目・河連法眼館(かわつらほうげんやかた)の段を
11時49分から13時まで、1,500円。
松竹座では『積雪恋関扉(つもるゆきこいのせきのと)』を14時10分から15時40分まで、
2,100円でした。
ここでは文楽の話を中心に。
今回の『義経千本桜』は“道行”と“河連法眼館”の2部構成。
“河連法眼館”は“狐忠信(きつねただのぶ)”とも呼ばれたりしていて、
歌舞伎でも人気のある演目です。
兄・頼朝から追われの身になった義経は、
幼いころに兵法を学んだ河連法眼の吉野の屋敷に匿われていました。
そこに訪ねて来たのが、家来の佐藤忠信。
母の看病で故郷に帰っていて、ようやく義経の前に顔を出すことができたと言うのですが…
義経は吉野への道すがらで忠信に静御前を預けたと思っています。
それを尋ねると忠信は預かった覚えはないとのこと。
怒った義経は目の前の忠信を裏切り者と決めつけて罰しようとしていたところ、
静御前がそこへ一人で現れました。
静御前の話によると、肌身離さず持っていた鼓を打つと忠信が必ず姿を見せ、
その音に聞き入っていたようです。
義経はそれを確かめるために静御前に鼓を打たせ、自らは奥でその様子をうかがうことに。
そこに白い狐がスーッと通り過ぎたかと思えばいつの間にか忠信が現れたので、
静御前は刀を振り上げてその正体を明かすように迫ります。
静御前が持っているその鼓は・・・桓武天皇の時代、
雨乞いのために千年も生きたオスの狐とメスの狐を狩り出してその皮で作られたもので、
自分はその鼓の子なのだと白状して狐の正体を現します。
長く天皇家にあったその鼓は平家討伐の恩賞として義経に下されたあと、
静御前の手に渡ったのですが、せめて鼓になった両親に孝行をしたいとの思いで
忠信に化けて静御前のお供をしていたのです。
これを聞いた義経が、静御前を守った褒美として狐に鼓を与えると、
喜んだ狐は義経一行が危機にあっても神通力で守ると言い残し、
鼓とともに天高くその場を去って行く・・・という筋書きです。
歌舞伎では忠信から狐への早替わりと、
狐が去るときの“宙乗り”という演出(役者が上から吊られた状態で花道を下がる)で、
市川猿之助や中村勘九郎(現・勘三郎)などが得意としていました。
(私は猿之助のそれでかなりの衝撃を受けたものです)
では、文楽ではどうだったかと言えば。
狐をやっていた人形遣いの桐竹勘十郎が舞台狭しと縦横無尽の大活躍。
人形の早替わりだけでなく、人形遣いの衣装も一瞬で替わります。
そして勘十郎自身も舞台で“宙乗り”を演じ、桜の花びらを散らしながら幕、という
文楽のイメージをはるかに超えるかのようなラストシーンは圧巻そのものでした。
衣装の早替わりは、付けられている糸を引っ張って一瞬に替わることから
“引き抜き”と呼ばれています。
歌舞伎ではよくある演出ですが、文楽の人形遣いの“引き抜き”は初めて見ました。
そのあと松竹座で観た『積恋雪関扉』は“引き抜き”満載の舞踊劇。
樹齢300年と言われる“小町桜”をめぐってのやりとりで、
逢坂山の関守が実は朝廷転覆を企む大伴黒主(市川團十郎)であり、
関守に会いに来たという遊女が実は小町桜の精(坂田藤十郎)という設定。
それぞれの豹変ぶりがとても絵になっていました。
ただ、この演目はちょっと難しいのか、居眠りするお客さんがチラホラと・・・。
というわけで、
偶然にも“桜”と“引き抜き”という共通点のあった、
今回のハシゴ観劇でした。
20周年記念@南座。
2011年12月17日 趣味
昨年に続いて、京都・南座で
『當る辰歳 吉例顔見世興行 東西合同大歌舞伎』夜の部を観て来ました。
今回の『顔見世』は、南座の新装開場20周年記念と銘打たれていて、
緞帳も新しくなっています。
実は私も今年で勤続20年でして(^^;
今回はその節目で“リフレッシュ休暇”を頂戴し、
月例の通院と合わせて『顔見世』観劇に充てることにしました。
3日間連続のみで取れるのですが2日目は土日を挟んで今度の月曜日、
仕事の都合で1日捨てざるを得ず、火曜日は出勤です。
さて、夜の部の演目は以下の5つ。
*楼門五三桐(さんもんごさんのきり)
*実盛物語(さねもりものがたり)
*元禄忠臣蔵・仙石屋敷(せんごくやしき)
*喜撰(きせん)
*らくだ
その中から『楼門五三桐』と『らくだ』を少しだけご紹介。
『楼門~』は石川五右衛門が南禅寺の三門の上から満開の桜を眺めてのセリフ
「絶景かな、絶景かな~」が有名な演目。
五右衛門はそこで父の仇(かたき)が真柴久吉(豊臣秀吉のこと)であることを知りますが、
その久吉が三門の下に巡礼姿で現れ、上と下での対面という短い内容です。
錦絵を見るかのような豪華絢爛なセットがそのまませり上がり、
久吉が下から現れるという演出。
20年前、平成の大改修を終えた南座での『顔見世』では、
先代の片岡仁左衛門が五右衛門を演じています(私も観に行きました)。
今回はその長男、我當が五右衛門で、三男の秀太郎が久吉。
これぞ歌舞伎の様式美というような情景でした。
『らくだ』は落語がベースになったお芝居。
上方では六代目・笑福亭松鶴のそれがよく知られているところですが、
これが東京に渡り、お芝居のほうでは江戸風味に味付けされたものがよく出されます。
しかし今回の『らくだ』は設定からセリフからすべてが上方風で、
およそ46年ぶりの上演だそうです。
ここに出て来る“らくだ”とは、
フグの毒に当たって死んだならず者の男のニックネーム。
その友人・熊五郎が“らくだ”の通夜をしてやろうということで、
通りがかった紙屑屋の久六を巻き込んでの大騒動に発展します。
“らくだ”の長屋のケチな家主宅に“らくだ”の死骸を持って行って脅し、
まんまと酒をせしめるなどハチャメチャな内容。
初めのほうは威圧的な態度の熊五郎に気弱そうな久六という立場だったのが、
酒が進むにつれてそれが逆転して幕となります。
熊五郎は片岡愛之助、久六は中村翫雀。
どちらも上方の役者でセリフもごくごく自然なもの。
愛之助のドスの利かせかたがかなり良かったです。
この芝居で酒を運んできた丁稚を演じるのは翫雀の長男・壱太郎(かずたろう)。
熊五郎に「残りの三升はどないしたんじゃ、はよ持って来んかいっ!」と言われ、
ブツクサ言いながら戻りつつ「三升、さんじょう・・・」とつぶやいていると、
ハッと向き直って座り「未だ参上(さんじょう)つかまつりませぬ」。
『仮名手本忠臣蔵・四段目』の大星力弥、つまり大石主税のセリフですが、
前の『仙石屋敷』で大石主税を演じていた壱太郎がそれを言うわけで(笑)
翫雀の久六が「アホなんか賢いんかわからん、親の顔が見たいわ」と言って
さらに笑いと拍手が起こりました。
歌舞伎というよりは松竹新喜劇に近いですね(笑)
『実盛物語』は尾上菊五郎の凛々しさと優しさ、
『仙石屋敷』は片岡仁左衛門と坂東三津五郎の息の良さ、
『喜撰』は中村時蔵の艶やかさと、長唄・清元の見事なコラボレーションが
それぞれ印象に残りました。
16時15分開演の21時45分終演で、都合5時間30分。
今回は日付が変わらないうちに帰宅することができました。
楽しむだけ楽しんでも早く帰れるに越したことはありません(^^;
『當る辰歳 吉例顔見世興行 東西合同大歌舞伎』夜の部を観て来ました。
今回の『顔見世』は、南座の新装開場20周年記念と銘打たれていて、
緞帳も新しくなっています。
実は私も今年で勤続20年でして(^^;
今回はその節目で“リフレッシュ休暇”を頂戴し、
月例の通院と合わせて『顔見世』観劇に充てることにしました。
3日間連続のみで取れるのですが2日目は土日を挟んで今度の月曜日、
仕事の都合で1日捨てざるを得ず、火曜日は出勤です。
さて、夜の部の演目は以下の5つ。
*楼門五三桐(さんもんごさんのきり)
*実盛物語(さねもりものがたり)
*元禄忠臣蔵・仙石屋敷(せんごくやしき)
*喜撰(きせん)
*らくだ
その中から『楼門五三桐』と『らくだ』を少しだけご紹介。
『楼門~』は石川五右衛門が南禅寺の三門の上から満開の桜を眺めてのセリフ
「絶景かな、絶景かな~」が有名な演目。
五右衛門はそこで父の仇(かたき)が真柴久吉(豊臣秀吉のこと)であることを知りますが、
その久吉が三門の下に巡礼姿で現れ、上と下での対面という短い内容です。
錦絵を見るかのような豪華絢爛なセットがそのまませり上がり、
久吉が下から現れるという演出。
20年前、平成の大改修を終えた南座での『顔見世』では、
先代の片岡仁左衛門が五右衛門を演じています(私も観に行きました)。
今回はその長男、我當が五右衛門で、三男の秀太郎が久吉。
これぞ歌舞伎の様式美というような情景でした。
『らくだ』は落語がベースになったお芝居。
上方では六代目・笑福亭松鶴のそれがよく知られているところですが、
これが東京に渡り、お芝居のほうでは江戸風味に味付けされたものがよく出されます。
しかし今回の『らくだ』は設定からセリフからすべてが上方風で、
およそ46年ぶりの上演だそうです。
ここに出て来る“らくだ”とは、
フグの毒に当たって死んだならず者の男のニックネーム。
その友人・熊五郎が“らくだ”の通夜をしてやろうということで、
通りがかった紙屑屋の久六を巻き込んでの大騒動に発展します。
“らくだ”の長屋のケチな家主宅に“らくだ”の死骸を持って行って脅し、
まんまと酒をせしめるなどハチャメチャな内容。
初めのほうは威圧的な態度の熊五郎に気弱そうな久六という立場だったのが、
酒が進むにつれてそれが逆転して幕となります。
熊五郎は片岡愛之助、久六は中村翫雀。
どちらも上方の役者でセリフもごくごく自然なもの。
愛之助のドスの利かせかたがかなり良かったです。
この芝居で酒を運んできた丁稚を演じるのは翫雀の長男・壱太郎(かずたろう)。
熊五郎に「残りの三升はどないしたんじゃ、はよ持って来んかいっ!」と言われ、
ブツクサ言いながら戻りつつ「三升、さんじょう・・・」とつぶやいていると、
ハッと向き直って座り「未だ参上(さんじょう)つかまつりませぬ」。
『仮名手本忠臣蔵・四段目』の大星力弥、つまり大石主税のセリフですが、
前の『仙石屋敷』で大石主税を演じていた壱太郎がそれを言うわけで(笑)
翫雀の久六が「アホなんか賢いんかわからん、親の顔が見たいわ」と言って
さらに笑いと拍手が起こりました。
歌舞伎というよりは松竹新喜劇に近いですね(笑)
『実盛物語』は尾上菊五郎の凛々しさと優しさ、
『仙石屋敷』は片岡仁左衛門と坂東三津五郎の息の良さ、
『喜撰』は中村時蔵の艶やかさと、長唄・清元の見事なコラボレーションが
それぞれ印象に残りました。
16時15分開演の21時45分終演で、都合5時間30分。
今回は日付が変わらないうちに帰宅することができました。
楽しむだけ楽しんでも早く帰れるに越したことはありません(^^;
11~12月にかけての10日間のあいだに落語会を2つ楽しんで来ました。
一方は至極正当派な、もう一方は・・・?
◆11月25日(金) 桂 吉朝 七回忌追善落語会@国立文楽劇場◆
『商売根問』桂 佐ん吉
『明石飛脚』桂 しん吉
『芝居道楽』桂 よね吉
『不動坊』桂 吉弥
『鹿政談』桂 あさ吉
~中入~
ご挨拶 吉朝一門(あさ吉、吉弥、よね吉、しん吉、吉坊、佐ん吉、吉の丞)
『質屋蔵』桂 吉朝(上映)
吉朝師匠が亡くなられたのは、2005年の11月8日。
今年が七回忌にあたります。
最後の高座はその12日前、国立文楽劇場だったそうです。
7人の弟子が一同に会しての文楽劇場の落語会は非常に盛況でありました。
吉坊、吉の丞のお二方を除く5人の高座は、
それぞれにやはり師匠のエッセンスを漂わせているものがあり、
ふとした口跡から師匠の面影を見ることができました。
筆頭弟子のあさ吉さんが最も噺家らしからぬ語り口なのは意外でしたが、
(今回初見です)
『鹿政談』は思っていた以上に良かったと思います。
スクリーンに映し出された吉朝師匠の『質屋蔵』は、
読売テレビ『平成紅梅亭』からの収録でした。
落語家の息を感じるはずの落語会での上映は不思議な感じもありましたが、
今にして思えば惜しむに余りあるような、吉朝師匠独特の雰囲気は伝わって来ました。
生の高座を味わいたかったです。
◆12月4日(日) 『鉄』の世界~梅團治・しん吉 二人会@天満天神繁昌亭◆
*趣味の演芸
『癪の合薬』桂 二乗(開口一番)
『金明竹』桂 しん吉
『竹の水仙』桂 梅團治
~中入~
*本気の鉄
『(鉄道新作落語)親子旅行』桂 しん吉
『(鉄道新作落語)鉄道親子』桂 梅團治
本気の鉄道写真スライドショー 梅團治、しん吉、小梅
今年で5回目の『「鉄」の世界』、もはや年中行事となっております(笑)
今回も前売りは完売とのこと。
“趣味の演芸”のほうは、しん吉さんも梅團治さんも“竹”が出て来る噺で、
鉄道新作落語もそれぞれ“親子”が題材となったのは偶然の一致なのかどうか。
しん吉さんの『親子旅行』。
70歳を迎えた記念に「鉄道旅行がしたい」という父親の問いに対して、
3人の息子がそれぞれに妙な答えを出して父親を悩ませます。
(この部分、『片棒』という噺がベースになっていると思われ)
「鉄の足袋(たび)は重たいでっせ」
「70歳と言えば古希、ということでコキ70(貨車)に乗ってもらいまひょ」等々。
この3人の息子、名前を“あきら”“とおる”“わたる”と言うんですが、
そこで一部から笑いが起きたのは、実は米朝師匠のご子息の名前だそうで(驚)
「ったく、どいつもこいつも」と父親が嘆いているところへその父親が出て来て、
「ワシの100歳記念の旅行はどうなったんじゃ?」と。
梅團治さんの『鉄道親子』。
“鉄道(てつみち)”という名前の高校3年生の息子を持つ父親が、
大学受験を控えるにもかかわらず休みごとに鉄道写真を撮影に行く息子を諌めるため、
「首に縄を掛けてでも連れ戻す」と言って、息子が居るはずの撮影地へ出かけます。
一般人には理解できない、しかし“鉄ちゃん”ならお馴染みの光景に眼を白黒させるも、
そこに走って来たSLの姿を見て感動してしまい、
「ミイラ取りがミイラになる」という言葉のとおり父親も“鉄ちゃん”に。
終いには息子を上回る熱の入れようで家族を困らせる、という噺。
今春に高校を卒業して父親である梅團治さんに弟子入り、
この日はスライドショーの解説に出ていた小梅君がモデルのようでした(笑)
いつもの鉄道写真カレンダー抽選会は残念ながらハズレだったので、
1部購入させていただきました。
一方は至極正当派な、もう一方は・・・?
◆11月25日(金) 桂 吉朝 七回忌追善落語会@国立文楽劇場◆
『商売根問』桂 佐ん吉
『明石飛脚』桂 しん吉
『芝居道楽』桂 よね吉
『不動坊』桂 吉弥
『鹿政談』桂 あさ吉
~中入~
ご挨拶 吉朝一門(あさ吉、吉弥、よね吉、しん吉、吉坊、佐ん吉、吉の丞)
『質屋蔵』桂 吉朝(上映)
吉朝師匠が亡くなられたのは、2005年の11月8日。
今年が七回忌にあたります。
最後の高座はその12日前、国立文楽劇場だったそうです。
7人の弟子が一同に会しての文楽劇場の落語会は非常に盛況でありました。
吉坊、吉の丞のお二方を除く5人の高座は、
それぞれにやはり師匠のエッセンスを漂わせているものがあり、
ふとした口跡から師匠の面影を見ることができました。
筆頭弟子のあさ吉さんが最も噺家らしからぬ語り口なのは意外でしたが、
(今回初見です)
『鹿政談』は思っていた以上に良かったと思います。
スクリーンに映し出された吉朝師匠の『質屋蔵』は、
読売テレビ『平成紅梅亭』からの収録でした。
落語家の息を感じるはずの落語会での上映は不思議な感じもありましたが、
今にして思えば惜しむに余りあるような、吉朝師匠独特の雰囲気は伝わって来ました。
生の高座を味わいたかったです。
◆12月4日(日) 『鉄』の世界~梅團治・しん吉 二人会@天満天神繁昌亭◆
*趣味の演芸
『癪の合薬』桂 二乗(開口一番)
『金明竹』桂 しん吉
『竹の水仙』桂 梅團治
~中入~
*本気の鉄
『(鉄道新作落語)親子旅行』桂 しん吉
『(鉄道新作落語)鉄道親子』桂 梅團治
本気の鉄道写真スライドショー 梅團治、しん吉、小梅
今年で5回目の『「鉄」の世界』、もはや年中行事となっております(笑)
今回も前売りは完売とのこと。
“趣味の演芸”のほうは、しん吉さんも梅團治さんも“竹”が出て来る噺で、
鉄道新作落語もそれぞれ“親子”が題材となったのは偶然の一致なのかどうか。
しん吉さんの『親子旅行』。
70歳を迎えた記念に「鉄道旅行がしたい」という父親の問いに対して、
3人の息子がそれぞれに妙な答えを出して父親を悩ませます。
(この部分、『片棒』という噺がベースになっていると思われ)
「鉄の足袋(たび)は重たいでっせ」
「70歳と言えば古希、ということでコキ70(貨車)に乗ってもらいまひょ」等々。
この3人の息子、名前を“あきら”“とおる”“わたる”と言うんですが、
そこで一部から笑いが起きたのは、実は米朝師匠のご子息の名前だそうで(驚)
「ったく、どいつもこいつも」と父親が嘆いているところへその父親が出て来て、
「ワシの100歳記念の旅行はどうなったんじゃ?」と。
梅團治さんの『鉄道親子』。
“鉄道(てつみち)”という名前の高校3年生の息子を持つ父親が、
大学受験を控えるにもかかわらず休みごとに鉄道写真を撮影に行く息子を諌めるため、
「首に縄を掛けてでも連れ戻す」と言って、息子が居るはずの撮影地へ出かけます。
一般人には理解できない、しかし“鉄ちゃん”ならお馴染みの光景に眼を白黒させるも、
そこに走って来たSLの姿を見て感動してしまい、
「ミイラ取りがミイラになる」という言葉のとおり父親も“鉄ちゃん”に。
終いには息子を上回る熱の入れようで家族を困らせる、という噺。
今春に高校を卒業して父親である梅團治さんに弟子入り、
この日はスライドショーの解説に出ていた小梅君がモデルのようでした(笑)
いつもの鉄道写真カレンダー抽選会は残念ながらハズレだったので、
1部購入させていただきました。
京都・南座で『當る卯歳 吉例顔見世興行 東西合同大歌舞伎』を観て来ました。
私にとって3年ぶりの『顔見世』です。
今年の『顔見世』は、後半の前売り開始日を忘れることなく電話したのが幸いして、
チケット(2等B・9,500円)を取ることができました。
月例の通院日に合わせて夜の部を取ろうとしたわけですが、
その後半前売り開始の数日前に例の事件がありまして、
予約の電話をしたら「市川海老蔵は休演ですがよろしいでしょうか」と
こちらが尋ねてもいないのに何度も念押しされました(苦笑)
私としては『顔見世』を観に行くことそのものが目的なので、問題無しです。
夜の部の演目は、
*外郎売(ういろううり)
*仮名手本忠臣蔵・七段目 祇園一力茶屋の場
*心中天網島(しんじゅうてんのあみじま)・河庄
*鳥辺山心中
*越後獅子
の5つ。
海老蔵が出演予定だったのは最初の『外郎売』で、代役は片岡愛之助です。
『外郎売』は市川宗家(市川團十郎の家)の歌舞伎十八番のひとつで、
早口言葉の長いセリフがこの演目の見せどころ。
しかも1980年以来演じているのは團十郎、海老蔵と尾上松緑だけ。
それを上方の役者である愛之助が初めて勤めるのですから、これは貴重。
例えて言えば『SLやまぐち号』の牽引機がC57ではなくDD51だったようなものかと(笑)
それでもしっかりと役をこなし、万雷の拍手を浴びていました。
『七段目』、今回の配役は、
大星由良之助・・・中村吉右衛門
おかる・・・坂東玉三郎
寺岡平右衛門・・・片岡仁左衛門
これ、有り得ないぐらい豪華なんですけど(笑)
私がどうしても夜の部を取りたかったのは、
この顔ぶれで『七段目』が観られるというのが大きな理由でした。
玉三郎じたいあまり観る機会が無いし。
歌舞伎を観るようになってから20年以上経ちますが、
玉三郎が出ている芝居を観たのは4年前の松竹座での1回きりです。
顔だけでなく立ち姿も綺麗だし、
しかも上背があってものすごくスラッと見える、玉三郎の“おかる”。
でもってかなーり妖しい雰囲気がするのです。
それを包み込むような吉右衛門“由良之助”の大人物ぶりも惚れ惚れします。
しかし、“平右衛門”“おかる”の兄妹のやりとりを聴いていると、
落語『七段目』がアタマの中をよぎってしまうのは何とかしたいところ(笑)
『河庄』の紙屋治兵衛は、坂田藤十郎の当たり役。
家のことを省みず小春(中村扇雀)という遊女に入れあげて、
ついには心中を決意して小春の居る北新地の廓『河庄』へやって来る。
頬かむりをして花道をトボトボと歩く治兵衛の姿は、
藤十郎の祖父・初代中村鴈治郎が「頬かむりの中に日本一の顔」と句に読まれたほど。
上方歌舞伎を代表する名場面です。
詳しい筋書きは省略しますが、この二人はこの場では別れることになります。
その間に立つのは治兵衛の兄である粉屋孫右衛門で、演じているのは市川段四郎。
治兵衛と別れるように小春を説得するため、侍の姿に化けて『河庄』を訪れるのですが、
慣れない格好ゆえのぎこちなさと実直な人柄を同時に表さねばならぬ難しい役です。
段四郎はそれがとてもよく出ていて良かったのですが、
セリフがどうしても上方っぽく聞こえなかったのが惜しいです。
『鳥辺山心中』は大正時代の作。
将軍家のお供で京に来ていた旗本・菊地半九郎(中村梅玉)が、
祇園のお茶屋で同僚の弟と些細なことから口論となり、四条河原で決闘するはめに。
相手を斬り殺してしまった半九郎は馴染みの遊女・お染(中村芝雀)とともに死を選ぶ、
というのが簡単な筋書き。
梅玉は品のある侍やお殿様がとてもよく似合う役者だと思っているのですが、
人柄が良さそうなはずが積りに積って逆上してしまう、という場面もこれまた似合う、
ってのは誉め言葉になるでしょうか(^^;
歌舞伎としては新しい部類に入る作品ながら、浄瑠璃もしっかりとあります。
その中、四条河原で半九郎・お染が死を決意する場面に流れる下座の音(胡弓?)が、
どことなく退廃的な感じがして。
その意味ではやはり新しさのある演目でした。
最後はおめでたい『越後獅子』、中村翫雀の舞に見送られるかのように終演。
手元の時計では22時38分でした。
開演が16時15分ですから、6時間23分の長丁場だったわけで。
自宅にたどり着いたのは終演のおよそ2時間後。
疲れはしましたが、とても贅沢なひとときを過ごすことができました。
私にとって3年ぶりの『顔見世』です。
今年の『顔見世』は、後半の前売り開始日を忘れることなく電話したのが幸いして、
チケット(2等B・9,500円)を取ることができました。
月例の通院日に合わせて夜の部を取ろうとしたわけですが、
その後半前売り開始の数日前に例の事件がありまして、
予約の電話をしたら「市川海老蔵は休演ですがよろしいでしょうか」と
こちらが尋ねてもいないのに何度も念押しされました(苦笑)
私としては『顔見世』を観に行くことそのものが目的なので、問題無しです。
夜の部の演目は、
*外郎売(ういろううり)
*仮名手本忠臣蔵・七段目 祇園一力茶屋の場
*心中天網島(しんじゅうてんのあみじま)・河庄
*鳥辺山心中
*越後獅子
の5つ。
海老蔵が出演予定だったのは最初の『外郎売』で、代役は片岡愛之助です。
『外郎売』は市川宗家(市川團十郎の家)の歌舞伎十八番のひとつで、
早口言葉の長いセリフがこの演目の見せどころ。
しかも1980年以来演じているのは團十郎、海老蔵と尾上松緑だけ。
それを上方の役者である愛之助が初めて勤めるのですから、これは貴重。
例えて言えば『SLやまぐち号』の牽引機がC57ではなくDD51だったようなものかと(笑)
それでもしっかりと役をこなし、万雷の拍手を浴びていました。
『七段目』、今回の配役は、
大星由良之助・・・中村吉右衛門
おかる・・・坂東玉三郎
寺岡平右衛門・・・片岡仁左衛門
これ、有り得ないぐらい豪華なんですけど(笑)
私がどうしても夜の部を取りたかったのは、
この顔ぶれで『七段目』が観られるというのが大きな理由でした。
玉三郎じたいあまり観る機会が無いし。
歌舞伎を観るようになってから20年以上経ちますが、
玉三郎が出ている芝居を観たのは4年前の松竹座での1回きりです。
顔だけでなく立ち姿も綺麗だし、
しかも上背があってものすごくスラッと見える、玉三郎の“おかる”。
でもってかなーり妖しい雰囲気がするのです。
それを包み込むような吉右衛門“由良之助”の大人物ぶりも惚れ惚れします。
しかし、“平右衛門”“おかる”の兄妹のやりとりを聴いていると、
落語『七段目』がアタマの中をよぎってしまうのは何とかしたいところ(笑)
『河庄』の紙屋治兵衛は、坂田藤十郎の当たり役。
家のことを省みず小春(中村扇雀)という遊女に入れあげて、
ついには心中を決意して小春の居る北新地の廓『河庄』へやって来る。
頬かむりをして花道をトボトボと歩く治兵衛の姿は、
藤十郎の祖父・初代中村鴈治郎が「頬かむりの中に日本一の顔」と句に読まれたほど。
上方歌舞伎を代表する名場面です。
詳しい筋書きは省略しますが、この二人はこの場では別れることになります。
その間に立つのは治兵衛の兄である粉屋孫右衛門で、演じているのは市川段四郎。
治兵衛と別れるように小春を説得するため、侍の姿に化けて『河庄』を訪れるのですが、
慣れない格好ゆえのぎこちなさと実直な人柄を同時に表さねばならぬ難しい役です。
段四郎はそれがとてもよく出ていて良かったのですが、
セリフがどうしても上方っぽく聞こえなかったのが惜しいです。
『鳥辺山心中』は大正時代の作。
将軍家のお供で京に来ていた旗本・菊地半九郎(中村梅玉)が、
祇園のお茶屋で同僚の弟と些細なことから口論となり、四条河原で決闘するはめに。
相手を斬り殺してしまった半九郎は馴染みの遊女・お染(中村芝雀)とともに死を選ぶ、
というのが簡単な筋書き。
梅玉は品のある侍やお殿様がとてもよく似合う役者だと思っているのですが、
人柄が良さそうなはずが積りに積って逆上してしまう、という場面もこれまた似合う、
ってのは誉め言葉になるでしょうか(^^;
歌舞伎としては新しい部類に入る作品ながら、浄瑠璃もしっかりとあります。
その中、四条河原で半九郎・お染が死を決意する場面に流れる下座の音(胡弓?)が、
どことなく退廃的な感じがして。
その意味ではやはり新しさのある演目でした。
最後はおめでたい『越後獅子』、中村翫雀の舞に見送られるかのように終演。
手元の時計では22時38分でした。
開演が16時15分ですから、6時間23分の長丁場だったわけで。
自宅にたどり着いたのは終演のおよそ2時間後。
疲れはしましたが、とても贅沢なひとときを過ごすことができました。
桂吉弥独演会@国立文楽劇場。
2010年11月26日 趣味国立文楽劇場で『桂吉弥独演会』を観て来ました。
昨年10月にはABCホールでの独演会を観に行ったのですが、
今回は文楽劇場であるということを知って前売りを買おうと思っていたら、
いろいろあってその時期を逃してしまい、それに気が付いたのが一昨日。
「しゃあない、当日券狙いや」ということで仕事を定時で切り上げまして、
18時30分の開演に余裕で間に合うように行ったところ、
あっさり買えた、というわけです(笑)
この日の番組。
桂 吉の丞『時うどん』
桂 紅雀『花色木綿』
桂 吉弥『くしゃみ講釈』
~中入~
(ゲスト)横山ホットブラザーズ
桂 吉弥『崇徳院』
『くしゃみ講釈』は、
或る男が講談師に恋路の邪魔をされたその仕返しをたくらむ話。
『崇徳院』は、
若旦那の恋わずらいをめぐり、その裏で繰り広げられるドタバタ。
百人一首にある崇徳院の歌
「瀬をはやみ 岩にせかるる 滝川の われても末に 逢わんとぞ思ふ」
を題材にした大きなネタです。
この日のゲストは横山ホットブラザーズ。
舞台で観るのは初めてでした。
TVでやってるのとほぼおんなじネタなんですが、
次の展開が完全に読めるにも関わらずやっぱり笑ってしまうというか。
で、横山ホットブラザーズと言えば、のこぎり演奏(笑)
お馴染みの音合わせのセリフ
「♪おーまーえーはーあーほーか」を
文楽劇場の客席で大合唱することになろうとは(笑)
感動するぐらいオモロかったです。
そんな賑やかな芸が終わった直後の吉弥さんの『崇徳院』でしたが、
しっかりと落語の世界の中に引き込まれるような心持ちがしました。
NHKの連続テレビ小説『ちりとてちん』でもかなり重要なキーワードとして
用いられたネタでもありますし、
何かいろいろな場面を想像しながらも話の中身に没頭できたような気がします。
文楽劇場は落語会をやるにはちょっと大きい感じがするのですが、
吉弥さんの師匠である故・桂吉朝さんが生涯最後の高座を務めたところなのだそうです。
それから5年。
さまざまな思いを抱えながら今回初めて文楽劇場での独演会を迎えたであろうことが、
パンフレットに記された吉弥さんの“ごあいさつ”からよく伝わってきました。
これから第二回、第三回と続けて行って欲しいなぁ、と思います。
昨年10月にはABCホールでの独演会を観に行ったのですが、
今回は文楽劇場であるということを知って前売りを買おうと思っていたら、
いろいろあってその時期を逃してしまい、それに気が付いたのが一昨日。
「しゃあない、当日券狙いや」ということで仕事を定時で切り上げまして、
18時30分の開演に余裕で間に合うように行ったところ、
あっさり買えた、というわけです(笑)
この日の番組。
桂 吉の丞『時うどん』
桂 紅雀『花色木綿』
桂 吉弥『くしゃみ講釈』
~中入~
(ゲスト)横山ホットブラザーズ
桂 吉弥『崇徳院』
『くしゃみ講釈』は、
或る男が講談師に恋路の邪魔をされたその仕返しをたくらむ話。
『崇徳院』は、
若旦那の恋わずらいをめぐり、その裏で繰り広げられるドタバタ。
百人一首にある崇徳院の歌
「瀬をはやみ 岩にせかるる 滝川の われても末に 逢わんとぞ思ふ」
を題材にした大きなネタです。
この日のゲストは横山ホットブラザーズ。
舞台で観るのは初めてでした。
TVでやってるのとほぼおんなじネタなんですが、
次の展開が完全に読めるにも関わらずやっぱり笑ってしまうというか。
で、横山ホットブラザーズと言えば、のこぎり演奏(笑)
お馴染みの音合わせのセリフ
「♪おーまーえーはーあーほーか」を
文楽劇場の客席で大合唱することになろうとは(笑)
感動するぐらいオモロかったです。
そんな賑やかな芸が終わった直後の吉弥さんの『崇徳院』でしたが、
しっかりと落語の世界の中に引き込まれるような心持ちがしました。
NHKの連続テレビ小説『ちりとてちん』でもかなり重要なキーワードとして
用いられたネタでもありますし、
何かいろいろな場面を想像しながらも話の中身に没頭できたような気がします。
文楽劇場は落語会をやるにはちょっと大きい感じがするのですが、
吉弥さんの師匠である故・桂吉朝さんが生涯最後の高座を務めたところなのだそうです。
それから5年。
さまざまな思いを抱えながら今回初めて文楽劇場での独演会を迎えたであろうことが、
パンフレットに記された吉弥さんの“ごあいさつ”からよく伝わってきました。
これから第二回、第三回と続けて行って欲しいなぁ、と思います。
桂梅團治独演会『梅満会』@ワッハホール。
2010年3月7日 趣味千日前のワッハ上方・ワッハホールで『桂梅團治独演会・梅満会』を観て来ました。
梅團治さんの落語家生活30周年記念ということで、
桂春團治師匠がゲスト出演。
桂 佐ん吉(開口一番)『いらち俥』
桂 梅團治『野崎詣り』
桂 春團治(ゲスト)『高尾』
~中入~
桂 梅團治『ねずみ』
柳家 紫文(ゲスト)『音曲』※都々逸など
桂 梅團治『時うどん』
『野崎詣り』は春團治師匠の十八番とも言えるネタ。
『ねずみ』は珍しく岡山が舞台のネタで、
登場人物の岡山弁は倉敷出身の梅團治さんならでは。
『時うどん』では銭をごまかす場面よりも、
うどん屋とのやり取り(というか後半のうどん屋の反応)がかなり笑えました。
誰でも知っている噺を爆笑に持って行くのはなかなか難しいでしょうが、
そのあたりはさすがです。
『野崎詣り』が終わったあとで春團治師匠が登場、ということは・・・
出囃子が当然『野崎村』なわけで(笑)
春團治師匠の落語を生で観るのは全く初めてで、
最初のうちはボソボソボソ・・・とした語りから
徐々にピッチを上げて噺の中へ引き込んで行く、その凄さのようなものを感じました。
それにしても羽織を脱ぐ仕草の何とも粋だったこと!
後半のゲスト・柳家紫文さんは東京の芸人さんで、
三味線を持って都々逸などを語る“音曲(おんきょく)”の方。
先週は天満天神繁昌亭の昼席に出演されていたそうですが、
その名も芸も私にとっては初めて見聞きするようなもの。
「火付盗賊改め方長谷川平蔵が、両国橋を歩いていますと・・・」というネタが
夢にでも出て来そうで(笑)
最後は踊り『かっぽれ』も披露されました。
落語という芸は観客の想像力に依ったりするところが大きいわけですが、
梅團治さんのマクラにあった「想像力の限界に挑戦(笑)」ってのは、
まさにそのとおりではないかと思います。
脳の活性化にもつながるかも知れません。
梅團治さんの30周年記念行事は落語会だけではなく、
今度は4月11日に京都・梅小路蒸気機関車館でSLを走らせるのだそうです。
“撮り鉄”の梅團治さん、
撮る側に回りたいけど自分が乗らなアカンのであまり嬉しくない、
なんて言うてはりましたが(笑)
梅團治さんの落語家生活30周年記念ということで、
桂春團治師匠がゲスト出演。
桂 佐ん吉(開口一番)『いらち俥』
桂 梅團治『野崎詣り』
桂 春團治(ゲスト)『高尾』
~中入~
桂 梅團治『ねずみ』
柳家 紫文(ゲスト)『音曲』※都々逸など
桂 梅團治『時うどん』
『野崎詣り』は春團治師匠の十八番とも言えるネタ。
『ねずみ』は珍しく岡山が舞台のネタで、
登場人物の岡山弁は倉敷出身の梅團治さんならでは。
『時うどん』では銭をごまかす場面よりも、
うどん屋とのやり取り(というか後半のうどん屋の反応)がかなり笑えました。
誰でも知っている噺を爆笑に持って行くのはなかなか難しいでしょうが、
そのあたりはさすがです。
『野崎詣り』が終わったあとで春團治師匠が登場、ということは・・・
出囃子が当然『野崎村』なわけで(笑)
春團治師匠の落語を生で観るのは全く初めてで、
最初のうちはボソボソボソ・・・とした語りから
徐々にピッチを上げて噺の中へ引き込んで行く、その凄さのようなものを感じました。
それにしても羽織を脱ぐ仕草の何とも粋だったこと!
後半のゲスト・柳家紫文さんは東京の芸人さんで、
三味線を持って都々逸などを語る“音曲(おんきょく)”の方。
先週は天満天神繁昌亭の昼席に出演されていたそうですが、
その名も芸も私にとっては初めて見聞きするようなもの。
「火付盗賊改め方長谷川平蔵が、両国橋を歩いていますと・・・」というネタが
夢にでも出て来そうで(笑)
最後は踊り『かっぽれ』も披露されました。
落語という芸は観客の想像力に依ったりするところが大きいわけですが、
梅團治さんのマクラにあった「想像力の限界に挑戦(笑)」ってのは、
まさにそのとおりではないかと思います。
脳の活性化にもつながるかも知れません。
梅團治さんの30周年記念行事は落語会だけではなく、
今度は4月11日に京都・梅小路蒸気機関車館でSLを走らせるのだそうです。
“撮り鉄”の梅團治さん、
撮る側に回りたいけど自分が乗らなアカンのであまり嬉しくない、
なんて言うてはりましたが(笑)
桂吉弥独演会@ABCホール。
2009年10月23日 趣味朝日放送の新社屋の中にあるABCホールで、
『徒然亭草原 桂吉弥独演会』夜の部を観て来ました。
夜の部のネタは、
桂 そうば『手水(ちょうず)回し』
桂 吉弥『天王寺詣り』
桂 ちょうば『片棒』
桂 吉弥『青菜』
~中入~
桂 吉弥『かぜうどん』
“独演会”と言っても吉弥さんひとりでずっと演じるのではなく、
前座(開口一番)も居れば着替え中のつなぎも居るわけでして。
吉弥さんが演じたネタ3本の中で、もっとも爆笑したのは『青菜』でした。
どう面白かったかを説明するのは難しいのですが(^^;
高尚な世界のことを庶民がやったらどうなるか、という典型みたいな話ですが、
その情景が目に浮かぶようで。
最後の『かぜうどん』は故・桂枝雀師匠のカラーがちょっと入ってるかな、とも。
ついつい噺の中に引き込まれてしまいました。
落語はテレビやラジオで見聴きする機会もあったりしますが、
やはりライブは違います。
ABCホールはそんなに大きなハコではありません。
それだけに演者の息が客席へ直に伝わって来るんですよね。
演者の独りよがりでは観客は付いて来ないし、
観客も楽しもうという姿勢が無ければ演者はやり甲斐がないし。
演者と観客の目に見えないやりとり如何で、その場がどうにでも変わったりするもので。
先日読了した堀井憲一郎の『落語論』にあったのですが、
「落語は、大人が集まって“集団トリップ”するための道具である」と。
ネタの字面を追って話しているだけではトリップできません。
いかに観客を想像の世界に引きずりこみ、トリップさせられるか、
それが落語家の腕にかかっていると言っても良いでしょう。
落語家はひとりで何人もの人物を使い分け、
扇子や手ぬぐいなど必要最小限の小道具であらゆる物事を表現しますから、
当然観客の側にも基本的な想像力は要求されるわけですが。
・・・とまぁ難しい話になってしまいましたが、
『かぜうどん』を観た客が「ああ、うどん食べたいなぁ」と思えるようになれば
上手くいった、ということになるのでしょう(笑)
私、実際そう思いましたし。
吉弥さん、茨木市の山手台とやらの出身だそうで、
『かぜうどん』のマクラで、アヒルのマークのクリーニング屋さんが
「♪僕はアヒルの洗濯屋」てな音楽を流しながらやって来るという話を
実演付きでしていました(笑)
「♪ゆーきーやコンコン」の灯油屋さんなら知ってるんですけどね(^^;
『
夜の部のネタは、
桂 そうば『手水(ちょうず)回し』
桂 吉弥『天王寺詣り』
桂 ちょうば『片棒』
桂 吉弥『青菜』
~中入~
桂 吉弥『かぜうどん』
“独演会”と言っても吉弥さんひとりでずっと演じるのではなく、
前座(開口一番)も居れば着替え中のつなぎも居るわけでして。
吉弥さんが演じたネタ3本の中で、もっとも爆笑したのは『青菜』でした。
どう面白かったかを説明するのは難しいのですが(^^;
高尚な世界のことを庶民がやったらどうなるか、という典型みたいな話ですが、
その情景が目に浮かぶようで。
最後の『かぜうどん』は故・桂枝雀師匠のカラーがちょっと入ってるかな、とも。
ついつい噺の中に引き込まれてしまいました。
落語はテレビやラジオで見聴きする機会もあったりしますが、
やはりライブは違います。
ABCホールはそんなに大きなハコではありません。
それだけに演者の息が客席へ直に伝わって来るんですよね。
演者の独りよがりでは観客は付いて来ないし、
観客も楽しもうという姿勢が無ければ演者はやり甲斐がないし。
演者と観客の目に見えないやりとり如何で、その場がどうにでも変わったりするもので。
先日読了した堀井憲一郎の『落語論』にあったのですが、
「落語は、大人が集まって“集団トリップ”するための道具である」と。
ネタの字面を追って話しているだけではトリップできません。
いかに観客を想像の世界に引きずりこみ、トリップさせられるか、
それが落語家の腕にかかっていると言っても良いでしょう。
落語家はひとりで何人もの人物を使い分け、
扇子や手ぬぐいなど必要最小限の小道具であらゆる物事を表現しますから、
当然観客の側にも基本的な想像力は要求されるわけですが。
・・・とまぁ難しい話になってしまいましたが、
『かぜうどん』を観た客が「ああ、うどん食べたいなぁ」と思えるようになれば
上手くいった、ということになるのでしょう(笑)
私、実際そう思いましたし。
吉弥さん、茨木市の山手台とやらの出身だそうで、
『かぜうどん』のマクラで、アヒルのマークのクリーニング屋さんが
「♪僕はアヒルの洗濯屋」てな音楽を流しながらやって来るという話を
実演付きでしていました(笑)
「♪ゆーきーやコンコン」の灯油屋さんなら知ってるんですけどね(^^;
吉例顔見世興行@南座。
2007年12月21日 趣味
京都・南座で『當る子歳 吉例顔見世興行』を観て来ました。
ここ数年、歌舞伎を観に行くと言えば大阪松竹座ばかりで、
南座には10年以上のごぶさた。
特に顔見世は安いほうのチケットがなかなか取れず、
“まねき”を撮ったり“番付(プログラム)”だけを買ったりする程度でした。
今回運良く買えた3等席は3階の正面最上段で、照明室の真下。
頭を動かさなくても舞台全体が見渡せるので、私にとっては良い席でした。
客席には和服姿の方も多く、とても華やいだ雰囲気です。
今年の顔見世は“二代目中村錦之助襲名披露”と銘打たれています。
ちなみに初代の中村錦之助は亡き萬屋錦之助のこと。
TVや映画での活躍をご記憶の方も多いかと思います。
ウチの母に言わせれば「若い頃はホンマ男前やった」そうですが。
二代目は初代の甥に当たります。
とても上品な顔立ちの役者さんです。
その襲名披露の口上が、夜の部第二の『寿曾我対面』の劇中でありまして。
一旦芝居を中断して(当然衣装はそのままで)口上を述べ、
それが終わるとまた何事もなかったかのようにまた芝居に戻る、と。
本当は不自然な流れであるはずなのですが、
そこは歌舞伎独特の楽しみとも言えると思います。
第三の『京鹿子娘道成寺』を演じるは坂田藤十郎。
御年77、つまり“喜寿”ですが、
舞台に姿を現したときのその美しさには溜息混じりの歓声が起こるほど。
『娘道成寺』は歌舞伎舞踊きっての大曲で体力も当然要るわけで、
それを思えばこの77歳はすごい、としか言いようがありませんでした。
踊りの途中で手ぬぐいが客席に投げられるのを見て、
「あー、あれを取ろうと思ったら特別席(24,150円!)でないと無理やなぁ」
などと考える3階最上段席の私。
いつもなら所化さん同士のやりとりで笑いを誘う場があるのですが、
今日は省略されていたのがちと残念でした。
最後の演目まで観終わって1階まで降りたところで、
「明日も来やはります?」などというお客さん同士の会話が耳に入ってきました。
京セラDの日本選手権じゃあるまいし、そんなに毎日来れるのかよと(苦笑)
おそらく役者さんのご贔屓筋の方なんでしょうねぇ。
また、「遅いときには11時回ってましたなぁ」とおっしゃる方も。
今回はまだ早いほうだったのかと(汗)
ついでに、当然ながら晩ごはんは幕間に済ませるのですが。
今回は顔見世出演中の市川左團次の屋号“?島屋”にちなんで、
京都?島屋の地下で巻寿司と箱寿司の詰め合わせを買ってきました。
コンビニの手巻き寿司じゃ気分が出ないものでね(笑)
ここ数年、歌舞伎を観に行くと言えば大阪松竹座ばかりで、
南座には10年以上のごぶさた。
特に顔見世は安いほうのチケットがなかなか取れず、
“まねき”を撮ったり“番付(プログラム)”だけを買ったりする程度でした。
今回運良く買えた3等席は3階の正面最上段で、照明室の真下。
頭を動かさなくても舞台全体が見渡せるので、私にとっては良い席でした。
客席には和服姿の方も多く、とても華やいだ雰囲気です。
今年の顔見世は“二代目中村錦之助襲名披露”と銘打たれています。
ちなみに初代の中村錦之助は亡き萬屋錦之助のこと。
TVや映画での活躍をご記憶の方も多いかと思います。
ウチの母に言わせれば「若い頃はホンマ男前やった」そうですが。
二代目は初代の甥に当たります。
とても上品な顔立ちの役者さんです。
その襲名披露の口上が、夜の部第二の『寿曾我対面』の劇中でありまして。
一旦芝居を中断して(当然衣装はそのままで)口上を述べ、
それが終わるとまた何事もなかったかのようにまた芝居に戻る、と。
本当は不自然な流れであるはずなのですが、
そこは歌舞伎独特の楽しみとも言えると思います。
第三の『京鹿子娘道成寺』を演じるは坂田藤十郎。
御年77、つまり“喜寿”ですが、
舞台に姿を現したときのその美しさには溜息混じりの歓声が起こるほど。
『娘道成寺』は歌舞伎舞踊きっての大曲で体力も当然要るわけで、
それを思えばこの77歳はすごい、としか言いようがありませんでした。
踊りの途中で手ぬぐいが客席に投げられるのを見て、
「あー、あれを取ろうと思ったら特別席(24,150円!)でないと無理やなぁ」
などと考える3階最上段席の私。
いつもなら所化さん同士のやりとりで笑いを誘う場があるのですが、
今日は省略されていたのがちと残念でした。
最後の演目まで観終わって1階まで降りたところで、
「明日も来やはります?」などというお客さん同士の会話が耳に入ってきました。
京セラDの日本選手権じゃあるまいし、そんなに毎日来れるのかよと(苦笑)
おそらく役者さんのご贔屓筋の方なんでしょうねぇ。
また、「遅いときには11時回ってましたなぁ」とおっしゃる方も。
今回はまだ早いほうだったのかと(汗)
ついでに、当然ながら晩ごはんは幕間に済ませるのですが。
今回は顔見世出演中の市川左團次の屋号“?島屋”にちなんで、
京都?島屋の地下で巻寿司と箱寿司の詰め合わせを買ってきました。
コンビニの手巻き寿司じゃ気分が出ないものでね(笑)
『鉄』の世界@繁昌亭。
2007年12月9日 趣味
『鉄』の世界/梅團治・しん吉 二人会
@天満天神繁昌亭
『開口一番』 桂 ひろば
〜趣味の演芸〜
『初天神』 桂 しん吉
『ひとり酒盛』 桂 梅團治
〜本気の『鉄』〜
『103系の嘆き』 桂 しん吉
『切符』桂 梅團治
『本気の鉄道写真スライドショー』 梅團治・しん吉
“天満天神繁昌亭”へ初めて行ってきました。
落語会へ行くのも本当に久しぶりでして。
(と言っても10年ぐらい前のNGKスタジオですが)
昔ほどではないにしろ“鉄分”がやや濃い目の私にとっては、
これが繁昌亭デビューの絶好のチャンスのようなものでした。
200人ちょっとが入るはずの客席は補助イスが出るほどの大盛況。
古典落語を“趣味”と言い切ってしまうその意気やよし。
『103系の嘆き』の桂しん吉さんは、故・桂吉朝師匠のお弟子さんで、
鉄道で旅をするのが好きな“乗り鉄”なのだそうです。
長い間大阪環状線を走り続けてくたびれてきた103系に、
地下鉄御堂筋線の10系?が地下から話しかけて進む筋立て。
同じグルグル回っていても山手線の電車にはモニターが16個もあって
京阪のテレビカーがひがんでる、などのネタをスライドも交えつつ。
最近の電車はドアの開閉が静かやから真似しにくい、といった
しん吉さん自身の嘆きも含まれたりします。
『切符』の桂梅團治さんは、桂春團治師匠のお弟子さん。
失礼ながら春團治一門とは思えぬほどの迫力ある声の持ち主で、
SLの写真を撮るのが専門の“撮り鉄”です。
ご本人いわく「3日前にできた話なのでトチッても誰もわからん」という新作。
さっきの『一人酒盛』で出てきた酔っ払いをここに登場させ、
後日談のようにして仕上げてきたことに場内は拍手喝采。
酔ってしまって自分の次の行先がわからない、ということで、
駅員に時刻表を持って来させて新大阪〜東京の各駅を順に言わせる趣向。
米原と熱海で時刻表のページが変わる細かい芸もありました。
そして、スライドショーでは梅團治さんが撮影されたSLの写真を
ご本人の解説を交えて上映。
『やまぐち号』の追っかけ撮影を何日も行うそのついでに、
現地で落語会をされたというエピソードもありました。
この会が12月になったのは、『やまぐち号』の運転が終了したからだとか(笑)
他にも福島、岩手、新潟などへ撮影機材一式を車に詰めて足を運ばれ、
プロ顔負けの写真を撮って来られています。
最後は梅團治さん撮影の写真入りミニカレンダーの抽選会。
私は残念ながら当たりませんでしたが(^^;
本気の『鉄』、かなり面白かったです。
昨年冬にオープンした地元のシネコンにようやく行ってきました。
最初のうちはどうせ混むだろうし、ほとぼりが冷めてから行こうと思いながら、
気が付けばまもなくオープンから80日が経とうとしています。
で、仕事の帰りに思い立ってちょっと寄ってみたのですが。
私が入ったシアターは217席あるところ、お客さんは20人ぐらいだったかな、と。
一応座席指定でもそんなの関係ないような様子で。
ぱっと見た感じ、年齢層はやや高めでした。
何を観たかと言えば、『愛の流刑地』(爆)
だってちょうど良い時間帯だったんだもん(^^;
昨年TVドラマで弁護士をやっていた豊川悦司(私の地元出身らしいですな)が、
今回は弁護される側に回っています。
で、その娘役として貫地谷しほりが出ていまして。
これがまた良い演技をしているんですわ。
ハセキョーの演技はとても見てられんかったけど
寺島しのぶは特別に美貌の持ち主ではないと思うのですが、凄いなぁ、と。
何というか・・・時を経るにつれての豹変ぶり、とでも言って良いのでしょうか。
いかにも“役者の血”というのをそこに感じた次第です。
私はどうしても“尾上菊五郎と富司純子の娘”という眼で見てしまいますが。
(実際、富司純子は寺島しのぶの実母役で出ています)
エンディングで平井堅の歌が流れ出すところは、
なんちゃらサスペンス劇場を見ているかのようで。
このあたりはNTVっぽいですね。
このシネコン、明日から“オープン80日祭”ということで、
500円または1,000円で観られる機会があるそうです。
今のところラインナップ中では3月の『寝ずの番』『フラガール』を観に行ければ、と
思っていますが・・・。
あと、ここで上映されるかどうかわかりませんが、
『バッテリー』(あさのあつこ・作)を観に行きたいです。
最初のうちはどうせ混むだろうし、ほとぼりが冷めてから行こうと思いながら、
気が付けばまもなくオープンから80日が経とうとしています。
で、仕事の帰りに思い立ってちょっと寄ってみたのですが。
私が入ったシアターは217席あるところ、お客さんは20人ぐらいだったかな、と。
一応座席指定でもそんなの関係ないような様子で。
ぱっと見た感じ、年齢層はやや高めでした。
何を観たかと言えば、『愛の流刑地』(爆)
だってちょうど良い時間帯だったんだもん(^^;
昨年TVドラマで弁護士をやっていた豊川悦司(私の地元出身らしいですな)が、
今回は弁護される側に回っています。
で、その娘役として貫地谷しほりが出ていまして。
これがまた良い演技をしているんですわ。
寺島しのぶは特別に美貌の持ち主ではないと思うのですが、凄いなぁ、と。
何というか・・・時を経るにつれての豹変ぶり、とでも言って良いのでしょうか。
いかにも“役者の血”というのをそこに感じた次第です。
私はどうしても“尾上菊五郎と富司純子の娘”という眼で見てしまいますが。
(実際、富司純子は寺島しのぶの実母役で出ています)
エンディングで平井堅の歌が流れ出すところは、
なんちゃらサスペンス劇場を見ているかのようで。
このあたりはNTVっぽいですね。
このシネコン、明日から“オープン80日祭”ということで、
500円または1,000円で観られる機会があるそうです。
今のところラインナップ中では3月の『寝ずの番』『フラガール』を観に行ければ、と
思っていますが・・・。
あと、ここで上映されるかどうかわかりませんが、
『バッテリー』(あさのあつこ・作)を観に行きたいです。
面白うて、やがて哀しき・・・。
2007年1月20日 趣味道頓堀・大阪松竹座で『壽 初春大歌舞伎』を観てきました。
“大阪松竹座新築開場10周年記念”という冠が付いています。
今回は幕見です。
市川團十郎の『勧進帳』が観られたら・・・と思っていたものの、
11時過ぎに松竹座の窓口へ行けば売り切れ。
(松竹座の幕見は12席しかありません)
しかし昼の第3部『封印切』の入手に成功。
1,700円でした。
それにしても、『封印切』はこれまで何度観たことやら・・・?
簡単に筋書きを言えば、
亀屋忠兵衛(坂田藤十郎)と井筒屋の傾城梅川(片岡秀太郎)は恋仲ながら、
丹波屋八右衛門(片岡我當)がその邪魔をする。
忠兵衛は八右衛門の挑発に乗った勢いで、
懐の中に預かっていた公金の封を切る重罪を犯してしまう。
あとは死を待つばかり・・・
と書けば悲劇っぽくなるのですが、そこは上方の芝居。
とくに前半はじゃらじゃらした艶っぽさや可笑しみの溢れる場面がふんだんに。
藤十郎の忠兵衛、我當の八右衛門はまさに当たり役で、
この両人のやりとりは何度観ても面白いです。
秀太郎の梅川、上村吉弥の井筒屋おえん、坂東竹三郎の槌屋治右衛門、と
役者の顔ぶれだけでも上方の匂いがぷんぷんと漂います。
それでも、忠兵衛が封印を切ってからの舞台からにじみ出るような物悲しさ。
忠兵衛と梅川は夫婦になるも決してハッピーエンドではないわけで。
しかし演じている藤十郎のセリフが、可笑しいやら哀しいやら。
なんとも言えぬ味わいがありました。
松竹座の初春大歌舞伎は1月26日まで。
当日券は・・・難しいかな。
“大阪松竹座新築開場10周年記念”という冠が付いています。
今回は幕見です。
市川團十郎の『勧進帳』が観られたら・・・と思っていたものの、
11時過ぎに松竹座の窓口へ行けば売り切れ。
(松竹座の幕見は12席しかありません)
しかし昼の第3部『封印切』の入手に成功。
1,700円でした。
それにしても、『封印切』はこれまで何度観たことやら・・・?
簡単に筋書きを言えば、
亀屋忠兵衛(坂田藤十郎)と井筒屋の傾城梅川(片岡秀太郎)は恋仲ながら、
丹波屋八右衛門(片岡我當)がその邪魔をする。
忠兵衛は八右衛門の挑発に乗った勢いで、
懐の中に預かっていた公金の封を切る重罪を犯してしまう。
あとは死を待つばかり・・・
と書けば悲劇っぽくなるのですが、そこは上方の芝居。
とくに前半はじゃらじゃらした艶っぽさや可笑しみの溢れる場面がふんだんに。
藤十郎の忠兵衛、我當の八右衛門はまさに当たり役で、
この両人のやりとりは何度観ても面白いです。
秀太郎の梅川、上村吉弥の井筒屋おえん、坂東竹三郎の槌屋治右衛門、と
役者の顔ぶれだけでも上方の匂いがぷんぷんと漂います。
それでも、忠兵衛が封印を切ってからの舞台からにじみ出るような物悲しさ。
忠兵衛と梅川は夫婦になるも決してハッピーエンドではないわけで。
しかし演じている藤十郎のセリフが、可笑しいやら哀しいやら。
なんとも言えぬ味わいがありました。
松竹座の初春大歌舞伎は1月26日まで。
当日券は・・・難しいかな。
←京都四条・南座の提灯と“まねき”
(12月10日撮影)
顔見世の雰囲気だけでも・・・。
“番付”はさすがに読み応え充分です。
南座の『顔見世』は今年も敢え無く断念。
しかし、来年1月の大阪松竹座『初春大歌舞伎』は
日程さえ合えば観に行けるだろう、と甘い考えなのであるが。
まだいつ行くかを決めかねている状態。
今度の松竹座の演目だが、
特に昼の部は初心者にも易しそうなものが並んでいる。
『毛谷村』は一応笑いどころはあるし、
『勧進帳』はストーリーが非常にわかりやすいし、
『封印切』はモロに上方の芝居だし。
3つを通しで観ても居眠りすることはないと思う(たぶん)。
まぁそれは良いとして、今回観に行きたいと思う演目は、
夜の部の『藤娘』という舞踊である。
このときだけは始まる直前に劇場内が完全に真っ暗になる。
長唄が静かに流れ出したと思ったらいきなり場内がパッと明るくなって、
紫の着物を着た“藤の精”が現れるという、暗転をうまく使った印象的な演目。
この瞬間のトキメキと言ったらそれはもう・・・何と表現して良いのやら。
今回の松竹座では中村扇雀が演じる。
私が歌舞伎を観はじめた10数年前は中村浩太郎(ひろたろう)という名前で、
お姫様役などさせてみたら思わず見とれてしまうぐらい綺麗な役者さんだった。
扇雀の『藤娘』はまだこの眼で観たことがないので、
“幕見”でも良いからぜひ観てみたいもの。
ここで来年の話をしても、もう鬼は笑わないとは思うが。
12月も残り20日を切ってしまったし。
(12月10日撮影)
顔見世の雰囲気だけでも・・・。
“番付”はさすがに読み応え充分です。
南座の『顔見世』は今年も敢え無く断念。
しかし、来年1月の大阪松竹座『初春大歌舞伎』は
日程さえ合えば観に行けるだろう、と甘い考えなのであるが。
まだいつ行くかを決めかねている状態。
今度の松竹座の演目だが、
特に昼の部は初心者にも易しそうなものが並んでいる。
『毛谷村』は一応笑いどころはあるし、
『勧進帳』はストーリーが非常にわかりやすいし、
『封印切』はモロに上方の芝居だし。
3つを通しで観ても居眠りすることはないと思う(たぶん)。
まぁそれは良いとして、今回観に行きたいと思う演目は、
夜の部の『藤娘』という舞踊である。
このときだけは始まる直前に劇場内が完全に真っ暗になる。
長唄が静かに流れ出したと思ったらいきなり場内がパッと明るくなって、
紫の着物を着た“藤の精”が現れるという、暗転をうまく使った印象的な演目。
この瞬間のトキメキと言ったらそれはもう・・・何と表現して良いのやら。
今回の松竹座では中村扇雀が演じる。
私が歌舞伎を観はじめた10数年前は中村浩太郎(ひろたろう)という名前で、
お姫様役などさせてみたら思わず見とれてしまうぐらい綺麗な役者さんだった。
扇雀の『藤娘』はまだこの眼で観たことがないので、
“幕見”でも良いからぜひ観てみたいもの。
ここで来年の話をしても、もう鬼は笑わないとは思うが。
12月も残り20日を切ってしまったし。
←永観堂 禅林寺(京都市左京区)の総門前にて
12月になっても、
紅葉がまだ残っていました。
久々にそこそこ好天の日曜日。
お昼前に家を出て、ちょっと京都まで。
とりあえずの目的は・・・
*『十八代目中村勘三郎襲名記念展』(美術館「えき」KYOTO)を観る
*南座で『顔見世』の番付を買う(今年も切符は買えず)
の2つだったが、そのあとも若干時間的な余裕があったので、
市バスに乗って永観堂まで行ってみた。
“秋は紅葉の永観堂”と呼ばれるほどの紅葉の名所だが、
私はなぜか今まで秋に行ったことがなかった。
盛りは過ぎていても、まだ見られるはずと信じて。
11月末までは寺宝展があった関係で拝観料が1000円と高かったが、
今日は通常料金に戻って600円。
有名な“みかえり阿弥陀”は、阿弥陀堂の工事のために瑞紫殿に移されていて、
ちょっと違った雰囲気で観ることができた。
観光シーズンのピークは過ぎているのだろうが、訪れる人は多い。
これが11月だったらもっと凄いことになっていて、
ゆっくりと観ることもできなかったかも知れない。
もっとも、帰りのバスは激混みでやって来て1本見送るほどだったのだが。
地下鉄の蹴上まで歩いても良かったかな・・・。
12月になっても、
紅葉がまだ残っていました。
久々にそこそこ好天の日曜日。
お昼前に家を出て、ちょっと京都まで。
とりあえずの目的は・・・
*『十八代目中村勘三郎襲名記念展』(美術館「えき」KYOTO)を観る
*南座で『顔見世』の番付を買う(今年も切符は買えず)
の2つだったが、そのあとも若干時間的な余裕があったので、
市バスに乗って永観堂まで行ってみた。
“秋は紅葉の永観堂”と呼ばれるほどの紅葉の名所だが、
私はなぜか今まで秋に行ったことがなかった。
盛りは過ぎていても、まだ見られるはずと信じて。
11月末までは寺宝展があった関係で拝観料が1000円と高かったが、
今日は通常料金に戻って600円。
有名な“みかえり阿弥陀”は、阿弥陀堂の工事のために瑞紫殿に移されていて、
ちょっと違った雰囲気で観ることができた。
観光シーズンのピークは過ぎているのだろうが、訪れる人は多い。
これが11月だったらもっと凄いことになっていて、
ゆっくりと観ることもできなかったかも知れない。
もっとも、帰りのバスは激混みでやって来て1本見送るほどだったのだが。
地下鉄の蹴上まで歩いても良かったかな・・・。
『UDON』
9月22日、関関戦の帰りに“ナビオTOHOプレックス”で観てきました。
その日は“TOHOシネマズなんば”のオープン日でしたが、
梅田から地下鉄で向かうと上映開始時間ギリギリだったもので。
簡単に感想を書きますと・・・
“オトナの付き合い”ができぬままに父親を亡くした身としては、
思わずウルウル来るようなシーンがありまして。
随所に『フィールド・オブ・ドリームス』の影響を感じた次第。
あと、高畑淳子や松本明子や南原清隆など、
ネイティブの讃岐弁を喋れるキャストがチョイ役のような感じで出演していたり。
(小西真奈美は地元の小学校を出ている設定なのに讃岐弁が出ない)
行ったことのある店や製麺所がいろいろ出てきたり。
10年ぐらい前、高松に住む大学の後輩に車を出してもらい、
“やまうち”や“山越”などに初めて連れて行かれたときには、
こんな映画ができるとは想像もしていなかったです。
ただ、あのCGは私にはちょっと理解でけんかったなぁ。
でも、まぁ面白かったですな。
9月22日、関関戦の帰りに“ナビオTOHOプレックス”で観てきました。
その日は“TOHOシネマズなんば”のオープン日でしたが、
梅田から地下鉄で向かうと上映開始時間ギリギリだったもので。
簡単に感想を書きますと・・・
“オトナの付き合い”ができぬままに父親を亡くした身としては、
思わずウルウル来るようなシーンがありまして。
随所に『フィールド・オブ・ドリームス』の影響を感じた次第。
あと、高畑淳子や松本明子や南原清隆など、
ネイティブの讃岐弁を喋れるキャストがチョイ役のような感じで出演していたり。
(小西真奈美は地元の小学校を出ている設定なのに讃岐弁が出ない)
行ったことのある店や製麺所がいろいろ出てきたり。
10年ぐらい前、高松に住む大学の後輩に車を出してもらい、
“やまうち”や“山越”などに初めて連れて行かれたときには、
こんな映画ができるとは想像もしていなかったです。
ただ、あのCGは私にはちょっと理解でけんかったなぁ。
でも、まぁ面白かったですな。
←羽田空港第2ターミナルのロビーにて
崎陽軒の『中華弁当』(1,000円)
駅で売られている弁当は“駅弁”であるのに対し、
空港で売られている弁当は“空弁(そらべん)”と呼ばれる。
その種類が最も豊富なのは新千歳空港、という話は聞いたことがあるが、
確かに私が初めて買った“空弁”は新千歳空港。
何だったかは忘れたが、カニとイクラが入った寿司だった気がする。
(ちなみに会社の旅行で、飛行機に乗ったのも実はそれが初めてだった)
仙台空港では牛タン弁当も買って食べたっけ。
しかし、羽田や福岡となると買うまでもない。
実質飛んでいるのは1時間にも満たないわけだし、
時間帯によってはその間に食べようと思えば食べられるのだが、
あまり周囲で弁当を広げているシーンを見たことがない路線でもあるし。
乗っている間は少しでも寝ておきたいしなぁ。
今回、羽田で初めて“空弁”を買った。
18時発の飛行機だから、機内で食べようと思えば食べれば良いし、
たとえ家へ持って帰ってもそんなに遅くならないから、と思ったもので。
たまたま目に付いたのが、1個だけ残っていた崎陽軒の『中華弁当』。
東京ドームで売られているのは同じ崎陽軒でも『横濱中華弁当』という名前で、
1,300円だった。
ドームの中だと何でも高いよなぁ、とブツクサ言いながらも
必要に迫られて買ったりするのだが、この弁当はとりあえず3年連続。
その『横濱〜』よりも箱が小ぶりな気がしたのだが、中身はほとんど同じ。
で、機内ではなく結局ロビーで食べました(^^;
予定の機材が延着したために準備が遅れ、
機内へ入れるのは出発予定時刻を過ぎてからになるとのこと。
じゃあその間に・・・と、ロビーの片隅にテーブルを見つけて食した次第。
崎陽軒だもの、まずいはずは無い(笑)
余談ながら、私は崎陽軒の『シウマイ』が好きだ。
大阪だと梅田の阪急百貨店の地下を出たところに売店があって、
通りがかるたびに無性に買って帰りたくなる。
『中華弁当』を食べても、シウマイだけは1個だけ最後に取って置く。
まるでそこらへんのガキと一緒である(苦笑)
さらに余談。
私が乗った飛行機には、西田尚美のようなCAは居なかったぞ(爆)
崎陽軒の『中華弁当』(1,000円)
駅で売られている弁当は“駅弁”であるのに対し、
空港で売られている弁当は“空弁(そらべん)”と呼ばれる。
その種類が最も豊富なのは新千歳空港、という話は聞いたことがあるが、
確かに私が初めて買った“空弁”は新千歳空港。
何だったかは忘れたが、カニとイクラが入った寿司だった気がする。
(ちなみに会社の旅行で、飛行機に乗ったのも実はそれが初めてだった)
仙台空港では牛タン弁当も買って食べたっけ。
しかし、羽田や福岡となると買うまでもない。
実質飛んでいるのは1時間にも満たないわけだし、
時間帯によってはその間に食べようと思えば食べられるのだが、
あまり周囲で弁当を広げているシーンを見たことがない路線でもあるし。
乗っている間は少しでも寝ておきたいしなぁ。
今回、羽田で初めて“空弁”を買った。
18時発の飛行機だから、機内で食べようと思えば食べれば良いし、
たとえ家へ持って帰ってもそんなに遅くならないから、と思ったもので。
たまたま目に付いたのが、1個だけ残っていた崎陽軒の『中華弁当』。
東京ドームで売られているのは同じ崎陽軒でも『横濱中華弁当』という名前で、
1,300円だった。
ドームの中だと何でも高いよなぁ、とブツクサ言いながらも
必要に迫られて買ったりするのだが、この弁当はとりあえず3年連続。
その『横濱〜』よりも箱が小ぶりな気がしたのだが、中身はほとんど同じ。
で、機内ではなく結局ロビーで食べました(^^;
予定の機材が延着したために準備が遅れ、
機内へ入れるのは出発予定時刻を過ぎてからになるとのこと。
じゃあその間に・・・と、ロビーの片隅にテーブルを見つけて食した次第。
崎陽軒だもの、まずいはずは無い(笑)
余談ながら、私は崎陽軒の『シウマイ』が好きだ。
大阪だと梅田の阪急百貨店の地下を出たところに売店があって、
通りがかるたびに無性に買って帰りたくなる。
『中華弁当』を食べても、シウマイだけは1個だけ最後に取って置く。
まるでそこらへんのガキと一緒である(苦笑)
さらに余談。
私が乗った飛行機には、西田尚美のようなCAは居なかったぞ(爆)
白井ヴィンセント、じゃないよ(笑)
昨日の夜は久しぶりに手紙を書いていた。
友人に何かを送る時、メモに簡単なメッセージを入れることはよくあるので
最近はメモや一筆箋のバリエーションが手元に増えている。
学生時代はなんやかんやと手紙を書く機会が多かった。
我ながらけっこう“筆マメ”だったと思う。
前回出したのと同じ便箋では芸が無い、といった変なこだわりもあって、
普通のレポート用紙からキャラクターものまで種々雑多に用意をしていたもの。
それがコンパクトなサイズになっただけかも知れない。
しかし、今度は適当な便箋を探し出す必要にかられた。
別に改まって書かねばならないような相手ではないが、
先日或るモノを貸してもらっていたので、それを返す際のお礼ということで。
今回用意できたのは白の横書きの便箋(某大学のロゴ入り)。
横書きになるとどうしても字が丸っこくなってしまう。
おまけに私の書く字は身体に似合わず小さいので、
できるだけわかりやすく書こうとはしているのだが・・・。
日記や仕事の文書などで横書きのものに毎日接しているわけだが、
いざ手紙を書いてみると、日本語の文字は縦書きが適しているなぁ、と
つくづく思う今日この頃。
たまには手紙も書かなきゃ、
“筆マメ”だった頃のカンが鈍ってしまうではないか(^^;
気をつけようっと。
昨日の夜は久しぶりに手紙を書いていた。
友人に何かを送る時、メモに簡単なメッセージを入れることはよくあるので
最近はメモや一筆箋のバリエーションが手元に増えている。
学生時代はなんやかんやと手紙を書く機会が多かった。
我ながらけっこう“筆マメ”だったと思う。
前回出したのと同じ便箋では芸が無い、といった変なこだわりもあって、
普通のレポート用紙からキャラクターものまで種々雑多に用意をしていたもの。
それがコンパクトなサイズになっただけかも知れない。
しかし、今度は適当な便箋を探し出す必要にかられた。
別に改まって書かねばならないような相手ではないが、
先日或るモノを貸してもらっていたので、それを返す際のお礼ということで。
今回用意できたのは白の横書きの便箋(某大学のロゴ入り)。
横書きになるとどうしても字が丸っこくなってしまう。
おまけに私の書く字は身体に似合わず小さいので、
できるだけわかりやすく書こうとはしているのだが・・・。
日記や仕事の文書などで横書きのものに毎日接しているわけだが、
いざ手紙を書いてみると、日本語の文字は縦書きが適しているなぁ、と
つくづく思う今日この頃。
たまには手紙も書かなきゃ、
“筆マメ”だった頃のカンが鈍ってしまうではないか(^^;
気をつけようっと。
皿うどんが、好きだ。
和泉屋の『長崎で作った皿うどんです。』。
近所のスーパーでこれを見つけて以来、
たまに買っているのだが。
これがなかなか美味い。
それまで、家で皿うどんを食べたいと思ったらどうしていたか?
具を揃えるのが面倒なので簡単に済ませる場合は、
スープ無しで売られている“揚げ麺”と“中華丼の具”をセットで買って・・・
という具合だった。
これでも皿うどんの雰囲気は味わえるが、どうもモノ足りない。
ところが、この和泉屋の皿うどんは具そのものが冷凍されている。
コップ一杯の水を沸騰させ、それに溶かせてとろみが付いたら出来上がり。
かなり本格的な皿うどんになる。
しかし。
大阪で食べられる皿うどんで言えば、やっぱり中央軒のほうが美味いんやなぁ。
作った人間の腕も勿論あるだろうが。
ともあれ、あのパリパリ麺は白飯に非常によく合うもので。
食べていると長崎へ行きたくなる(笑)
18日のオープン戦(ホークス二軍vs三菱重工長崎@ビッグN)、
行きたいけどなぁ。
和泉屋の『長崎で作った皿うどんです。』。
近所のスーパーでこれを見つけて以来、
たまに買っているのだが。
これがなかなか美味い。
それまで、家で皿うどんを食べたいと思ったらどうしていたか?
具を揃えるのが面倒なので簡単に済ませる場合は、
スープ無しで売られている“揚げ麺”と“中華丼の具”をセットで買って・・・
という具合だった。
これでも皿うどんの雰囲気は味わえるが、どうもモノ足りない。
ところが、この和泉屋の皿うどんは具そのものが冷凍されている。
コップ一杯の水を沸騰させ、それに溶かせてとろみが付いたら出来上がり。
かなり本格的な皿うどんになる。
しかし。
大阪で食べられる皿うどんで言えば、やっぱり中央軒のほうが美味いんやなぁ。
作った人間の腕も勿論あるだろうが。
ともあれ、あのパリパリ麺は白飯に非常によく合うもので。
食べていると長崎へ行きたくなる(笑)
18日のオープン戦(ホークス二軍vs三菱重工長崎@ビッグN)、
行きたいけどなぁ。
1 2